安楽死についてどう思うか。
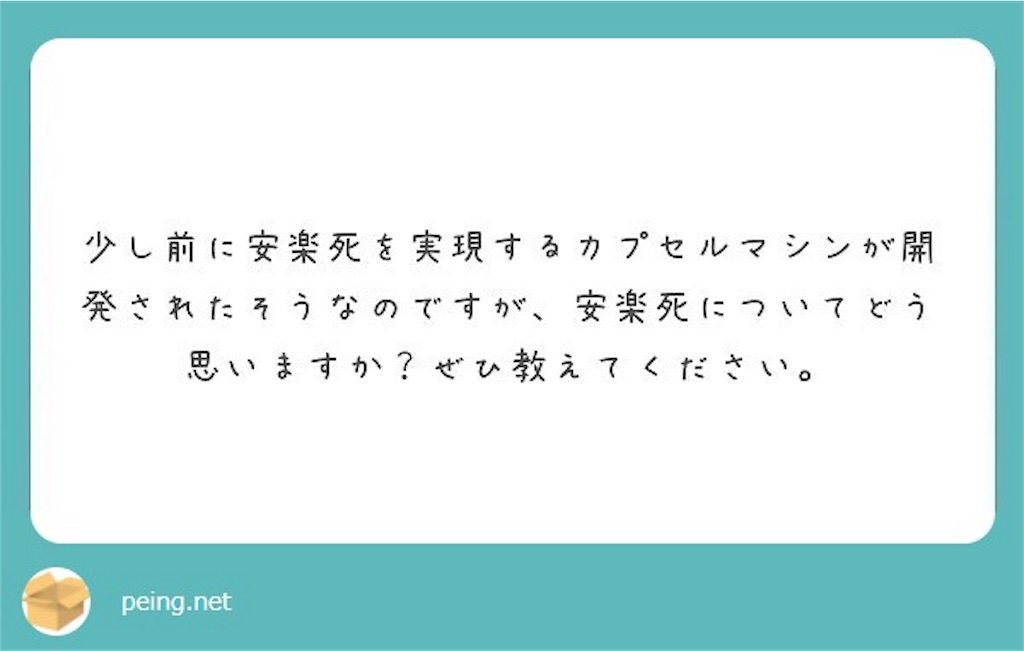
https://peing.net/q/2946b40a-6ca3-4862-845c-db6dff82142d
クリスマスに回答するようなご質問でもないかもしれませんが。(しばらく気づかず、すみません。)
元のニュースを存じ上げなかったのですが、そんなカプセルが開発されていたんですね。(カプセルというので薬のことかと一瞬思いましたけれど、そうではなくてこちらのことかしら:http://karapaia.com/archives/52250373.html)
安楽死、尊厳死、自殺幇助。言い方やニュアンスは少しずつ異なってくるものの、結局のところ人間に「死ぬ権利」なんてものはあるのか、という話だと感じています。
とはいえたとえば身投げして自殺したとしても「罪」にはならないのですが、これを良い事だととらえる人もあまりいないでしょう。自殺しなくてもよい道があればそちらを選んでほしい、と思うのが「自殺」に対するたいていの人の感情かと思います。
まずは比較的条件を単純化した話としてよくあげられる、「治療不可能かつ緩和治療の存在しない病に冒された、肉体的・精神的な苦痛がある(あるいは予定されている)、すでに余命宣告された人間」はどうしてその尊厳のために死んではならないのか、という仮定話から始められればと思います。延命措置を中止するという形での消極的安楽死はいちおう日本でも認められていますが、そこからもう一歩踏み込んでいる形です。
単純に自分のことに置き換えた場合、そういう状況では「死にたい」と思いそうです。実際そういう状況に陥ったときにどうするかはまだ分かりませんが、残り五十年とんでもない激痛のなかで生きるか、一年元気に暮らしたあと死ぬか、と二択を与えられたら後者を選びますので、少なくともわたしが「状況はどうでもいいからとにかく長く生きたい」と思っているわけではないことはたしかです。たぶん、たいていの人がそうでしょう。
しかし自分にとって大切な人間の顔を思い浮かべると、これは相手によっても違うのですが、なんだっていいから生きていて欲しいと思う相手と、苦しいから死にたいというなら罪になったっていいから死なせてやりたい相手と、両方いるような気がします。
なんだっていいから生きていて欲しいと思う相手、というのは結局のところ、とにかく生きていてくれさえすればいいと思ってしまうような愛情のある相手です。ふかい愛情ですが、ある意味では身勝手かつ盲目的な感情であり、相手の苦しみよりも自分の感情のほうを優先させてしまいたいということです。でもこれは文句なしに愛情の一種です。
苦しいから死にたいというなら罪になったっていいから死なせてやりたい相手というのは、できる限り幸せな人生を歩んで欲しいと思っている相手で、苦しいからもういやだというのならその助けをしてやりたい、と思う相手のことです。たぶん、わたしは彼らにとってよい人間でありたくて、最後まで役に立つ人間でいてやりたいと感じているんだと思います。これも愛情の一種です。
書いていて気づきましたが、原則的にはなんだっていいから生きていてほしいものの、苦しいから死にたいと頼まれたら手伝う、でももしもその人が他の人に手伝われて死んでしまったらきっとその「他の人」を生涯殺人者として許さないだろうと、そんなふうに思う相手もいますね。これは愛情とは何かということに結びついているので、なかなか個人的な感情部分に立ち入った話になります。しかしこれらはすべて客観的な「死」の話であり、当事者の視点を欠いています。
「本人の権利」と「残されたほうの権利」とでは、当然に「本人の権利」が優先されるべきです。そして、極端に考えて、五十年の耐え難い激痛と一年の健康余命とでは後者を選ぶ人がきっと多いことを考えるなら、たぶん私たちには「苦しいから死なせてくれ」という人から死を奪う権利はないんじゃないか、と思うことがあります。今はそう思っていますが、しかしこれは考える日によって違っていて、「いや、必ずしも当人の気持ちだけを信じて生死を取り扱うのは冒涜的なのではないか」と思う日もあります。
ここには二つの問題があると感じています。
ひとつめは宗教的な問題です。教理として自殺を禁じている宗教があります。これはとても分かりやすい指標になるかと思います。しかし残念なことにわたしは宗教を持っていなくて、縛ってくれる神もいません。
ふたつめは、正直なところ一つ目の問題と同質的でもあるのですが、死の後を知らないがために、命の大切さというものを結局のところだれも証明できないということです。死後の世界、死生観、というものは結局のところ宗教観に近しいところもあると思いますので、だから一つ目のものの言い方を変えているだけの話なのかもしれません。
日本人には無宗教の人が多いといわれていますが、それでも死を軽々しく扱う人はほとんどいません。神を信じているいないに関わらず、命が大切なものであると、感覚的に理解できているからです。しかし命が大切であることは真であっても、「痛みを伴い、本人が無意味だと感じている命」にどう価値をつけるべきか、他者からの評価で決めていいのか、しかし愛してくれる他者すらいない場合はどうしたらよいのか(本人の判断だけで決めてよいのか?)、逆に周囲がどうしても長く生きてくれという場合と本人の意思とのバランスはどうとればいいのか、そういった問題は結局「命は誰にとって大切なものなのか」という問題になるような気がしています。
もう少し考えるために、「治療不可能かつ緩和治療の存在しない病に冒された、肉体的・精神的な苦痛がある(あるいは予定されている)、すでに余命宣告された人間」に付与されていたさまざまな仮定をひとつずつ外していきます。「激痛はあるが死期が近くない場合」「死期は近いが痛みなどはない場合」「激痛を伴う病で死期は近いが、万が一の治療法がある場合」などに、安楽死の適応を可とするかどうかは、人によって結構意見が違うのではないでしょうか。わたしは特に「死期は近いが痛みなどはない場合」に死にたいと本人が言っても、死なせるべきではないと考えているような気がします。どうせ一年後に死ぬんだからいま死んだっていいじゃないか、といわれたとしても、本人がどれほど死なせてくれといったところで、それを丸呑みして自殺幇助をすることは許されないことのような気がしています。つまりわたしは「激痛を伴う命」よりは「安らかな死」のほうを尊重したいと思ってはいるのですが、「単純な前倒しの死」は許すことができず、あるいは「確定された死の恐怖への怯えを取り除いてやること」には興味がないということなんだと思います。他人の命のことなのに「許せない」なんて不思議ですよね。
しかしこう書いて思うこととして、「激痛」ってなんでしょうね。しばらく曖昧な定義のまま書いてきましたが、やっぱり「生きていられないほどの痛み」、それも肉体的・精神的な痛みって、ほんとうに人間に弁別できるものなんでしょうか。閾値を決めるのがものすごく難しい気がしますし、「**以上の痛みならば安楽死OK」とか決めるのもしっくりきていなかったり、またたとえば「六十歳以下ならS以上の痛みでないと安楽死できないが、六十~八十歳ならA以上の痛みで可、八十以上の場合はB以上なら可」とかいうテーブルが出来そうだなと思うと、またこれも尊厳が軽んじられているような気持ちになってしまいます。
また、「五十年の耐え難い激痛」と「一年の健康余命」という極端すぎる例は現実には存在せず、たいていは「外出はできないがなんとか一日に一時間家族と話したりすることはできる半年」と「外出はできないがなんとか一日に一時間家族と話せるところから、少しずつ痛みが強くなっていき最終的には激痛となる余命三年」と、みたいなバランスだったりすると思うので、そういう場合にいったいどちらを選ぶのか、また安楽死を選んでもいい閾値はどこなのか、ということを、みなが納得するように一意にすっぱりと決めることはおそらく不可能だと感じています。誰にとっても「それはやりすぎでは」「もう少し認めてもいいのでは」と思わせる閾値にしかならないということです。
一旦視点を変えて、「死ぬ権利」の反対のことを考えてみます。たとえば「死ぬ義務」や「生まれる権利」や「生まれる義務」はあるのか、という話です。
「生まれる権利」や「生まれる義務」は、命が女性の腹に宿るという都合上から、母体の権利も合わせて考える必要が出てきます。つまり、「生まれる権利」「生まれる義務」は、「生む権利」「生む義務」(あるいは「生まない権利」)と近しい問題になってきてしまう、ということです。
しかし上記の問題は母体と胎児とが不可分な関係にあるから発生するもので、たとえば子供が木になったり、あるいは泥のなかから這い出てくるようであれば、「宿した人間」と「宿った人間」との権利と義務との折衝を考える必要などないのです。
あんまり主張したことも表現したこともなかったかと思いますが、わたしはこの世界において女性と胎児とが不可分の関係であることに怒りのような不思議な気持ちを勝手に抱いていて、だから一部の創作世界のなかでは「子供は女性から生まれてくる」という現実世界の設定を完全に排除しています。そのほうが命というものについて、もう少し公平にシンプルに考えることができると思うからです。たとえば、人の数が増えすぎたと感じたときに、木になっている子供の果実を、あるいはできかけの泥の胎児を、間引いてしまうことは罪なのかどうか。そういう風に物事を考えたほうが単純に生まれる命だけに向き合っていられるような気がします。気のせいかもしれませんが。人を間引いてはいけないのだとしたら、たとえば生まれてくるまで人間なのか動物なのか植物なのかわからない木が一本あるとして、そこになる果実には一切手を触れてはいけないのか、しかしほうっておいたら木が倒れてしまいそうなとき、あるいは世界から食料がなくなってしまいそうなとき、いったいどう間引くのが正解なのか。そういうようなことをずっと考えていました。(ちなみにわたしは人間の命と、動物の命と、植物の命とは、完全に別次元のものとして尊重している部分があり、そのために上記のような書き方になっていますが、哺乳類の命までは人間の命と同じ程度に尊重したい、と思うひともいるでしょう)。が、これは「生まれる」ときの話なので、命の話ではあっても、「死の選択」の話とはまた別個のことですね。
また逆に、「死ぬ義務」はあるのか。これも考えたことがあります。実際的にはしばらく議論されることはないかと思いますが、たとえば今後の未来のどこかで、人間が半永久的に生きられるようになったとしても、現実的にはすべての人間に永久に生きていられては困るわけです。生きられる人間の数が決まっているとすれば、「生まれる権利」と「死ぬ義務」の折衝を行わなくてはならない可能性があります。「生き続ける権利」が誰にあるのかという話です。現状存在しない命に権利を与えるのか、いま生きている命の存続を大切にするのか。これも考えたくて、永遠に生きる人々の物語をいくつか考えてみましたが、結局罪人が一人出たら死刑を執行して少しずつ世界をよりよくしようと企む、乾いた生き物しか生まれませんでした。あるいは「命を達成した」順から死んでいくので、命を達成できない、つまり生きるのが下手な人間はいつまでも死ぬことができないという絶望的な方向に設定が進んでいきました。
考えた結果、「死ぬ義務」を誰かに背負わせるのだとしたら、それは出来の悪い人間を間引くような性質のことか、もしくは、熟した果実を収穫するように死んでもらうか、その二択のどちらかになってしまうと思うのです。
結局のところ、わたしが何度考えても結論があいまいにしか出ない問題として、「人は死んではいけないのだろうか」「幸せにならないまま死んでもかまわないのだろうか」のふたつがあります。あんぱんまんの歌のような話ですが、つまりなぜ生まれてきたのかということです。
結局それは手を変え品を変え、さまざまな主張を、作品のなかで続けていくしかないのかなあと感じています。「愛とはなにか」ということと、「命とはなにか」ということ、結局それは書いていくしかどうしようもない。しかし、愛とはなにかに答えを出せなくても誰も実際的には困らないのかもしれませんが、命とはなにかという問いには、そろそろ答えを出さなくてはならない時代になっているのかもしれませんね。
だいぶ話がそれましたね。
戻しますと、話を分かりやすくした、「治療不可能かつ緩和治療の存在しない病に冒された、肉体的・精神的な苦痛がある(あるいは予定されている)、すでに余命宣告された人間」については、とくに肉体的な苦痛が大きい場合には、条件の精査はあれど安楽死を認めるべきではないかと思っています。しかし精神的な苦痛においては答えが出せずにいます。(あるいは答えが出ても考えるたびに違っていたりします)。ただ、なににせよ閾値を決めるにあたっては、「生きるのが苦しい人間はその尊厳のために死んでもいいのか?」という問題に近しくなってしまうと考えています。話がひどく跳躍しますが、はたして幸せではない人間は生きていてはいけないのか、幸せになれる見込みのない人間は生きるべきではないのかという、そういう問題です。しかし、肉体的ではなくて精神的な部分において、生きるのが苦しくてどうしようもないな、もう詰んだだろうな、とおもう人間でも、しばらくするといろんなめぐり合わせがあって生きることが簡単になり、あのとき死ななくてよかったな、と思えるようになったりすることを、わたしは知っていて、だから単純に誰にでも安楽死が出来るようにすることは反対なのですが、それはわたしの身勝手なわがままのひとつなのかもしれませんし、ただしい、もしくは少なくとも妥当性のある主張であると証明できずにいます。わたしが主体的に出来るのは、「ひょっとすると死ななくてもいいかもしれませんよ」ということを、作品を通じて書いていくことしかないのかもしれなくて、それゆえに幸せではなくても生きていてもいいということを書きたいのですが、これはストーリーなしに単調に正確にお伝えすることはきわめて難しくて、小説という形をとらせてもらえればと思います。何度か書きましたけれども、思春期の女の子の気を一時逸らして、死なずにすませて時間を進ませ、あの陰鬱な夜を乗り越えるための一冊を作ることが、わたしの人生の目標です。
あんまりお答えになっていないかもしれませんが、たぶん以上が、わたしが今まで「死」について考えてきたことのなかで、ちゃんと言葉として書けるぶんのすべてです。ご質問ありがとうございました!
■
あなたに手紙を書く気持ちになりました。生涯渡すことのない手紙だと思います。いつだったかあなたがわたしに下さった手紙の返事を、そういえばしていないことに気がついたのです。あの手紙はいつまでも保管しておきたいとおもうほど、与えられた勲章のように輝いています。そんな白い感情のうら、あなたにたいしては嫌悪や憎悪もおなじぐらいにうずまいていて、つまり総合するとわたしはあなたのことが大嫌いなのですが、それはともかく、返礼をしないのは礼儀を欠いたことでしょうから、遠回りになりましたが、つまりこれはわたしのための、わたしのなかのあなたを整理するための葬式です。なんて書いたらさすがに、お見せすることはないにしたって、あなたの気分はよくはないかもしれません。
さて、手紙を書くにあたってあなたとの出会いのところから思い返してみました。もう何年もまえに、初めて会ったときのことを、わたしのほうは覚えています。円卓を囲んで、わたしは緊張していて、しかしやさしい顔をしたあなたがたと初対面し、わたしは自分のやりたいことをいえませんでした。しかしそれでもさしたる問題はなかった。わたしにはやりたいことなんて――これは、もうずっと言いつづけていることなので、もちろんご存知でしょうが――わたしには、ひとつもないからです。
いまでもわたしにはやりたいことなんてないままですが、わたしが一つこの数年間であなたから学んだことをおつたえするなら、それはやってみなくては、じぶんがそれに向いているかどうかなどわからないということです。わたしは自分が自分でいられることに感謝していました。いや、感謝なんていうと不思議なことですね。どちらかというと、すくなくとも私がものたりない人間ではなかったことに安堵していたのです。長い人生を歩むにあたって、プレイヤーがわたしという個人であること、じぶんでいることはわたしにとって嬉しい、やさしい、有意義なことでした。そしてそんな唯一なる自分の、できることがふえるのは、うれしいことでした。
見渡すかぎりの大勢の人の前に立って話をすること、つよく相手に威圧をかけて言うことを聞かせること、あいての揚げ足をとって自分ののぞむ方向に進めること、きっと十年まえのわたしがきいたら、ぜったいに出来ないというでしょう。なんならわたしは他人と電話をすることすら嫌いで、どうしようもできなくて、自分にはそういう能力が欠如しているのだと、そんなふうにすら思っていたのです。
しかしそんな思い込みは誤りだったと、わたしはすでに知っています。わたしには出来ることが、じぶんがおもうよりもたくさんあった。それを知ることができたのは幸いでした。ぎゃくに、自分に向いていると思っていたことが、じつはそうではなかったと知ることもありました。しかし落胆はできなかった。自分のことをより深く知ることこそが大事なことであり、自分の欠損を見せ付けられても、それはそれで愛することができたからです。どうしてなのかは分かりません。この自己愛の源泉について、わたしはついに解明することができませんでした。
自己愛、というとすこし齟齬があるのかもしれなくて、わたしは結局、じぶんのことをこれ以上ないほど承認しているのです。
だから、わたしは自分にはなんの不満もありません。しかしそれでもどうしてか、わたしは人生のよい進み方をみつけられそうにありません。わたしは何が出来ればしあわせで、なにをやりたくて、どういうことを考えたくて、生まれてきてしまったのか。ほんとうにそのすべてが分からない。あるいはそれは、この承認の反作用、副作用なのかもしれなくて、すべてを投げ捨てていちからはじめてみれば、なにかの「ありがたみ」というやつが分かるのではないかと思ったこともあります。
異国に行きたいのです。
あなたは外れたレールだと笑うでしょう。あなたがたくさんの人を、あんなふうに生きてどうするつもりだと笑うのを見てきました。まったくわたしも同感です。しかしあなたが笑えば笑うだけ、わたしは閉塞したきもちになり、そしてまさに「はずれ」た、あなたや、わたしからみたらどうしようもないほど「はずれ」きったひとに、あなたが反旗をひるがえされたとき、わたしは不思議なきもちになりました。自ら「はずれ」なくとも、単なる不運で、「はずれ」ることもあるのです。
わたしはあなたに言ったことがある。もしかして、わたしたちがまともでいるようなつもりになっているのは――いや、あなたからしたら、わたしはまったくまともではないそうですが、しかし、まともでいる人間とそうでない人間というのは、たんなる運によるものなのではないでしょうか。あなたはいろんな文句をつけて他人を評論するのがすきですが、よいステータスの人間でいることがすきですが、しかしそれはほんとうにあなたの手によるものなのでしょうか。わたしはたまに分からなくなっていたのです。あなたはわたしのことばを聞いて、なんとなく納得したような顔も見せていましたが、しかし人間の努力のちからについてわすれてはならないとわたしに釘をさしました。しかしわたしはずっとあの日から考え続けていた。自分の運のよさと、そして運が悪かったひとへのあなたのまなざしのつめたさについて。
レールから「はずれ」るのではなくて、単におみくじのように、なにかが決まってしまうなら、「はずれ」をひいた人に、わたしたちは感謝こそすれ、あざわらうことなど許されるわけはないのです。
君はより運がよいからそんなふうにおもうのだ、とあなたが言ったのをわたしは覚えていて、覚え続けていて、たしかにわたしの人生は、根源的に幸運の連続でした。たまたまよい両親のもとに、たまたまよい環境に、たまたまよい友人に恵まれ、たまたま進んだ学校とたまたま見つけた会社、そのすべての「たまたま」が折り重なって、わたしの意志などとは関係なく、なにかが一方向にわたしを引っ張っているように思うことすらあります。でも、あなたが言うほどわたしはあやつり人形でもない。わたしはそれなりに自分で決断をしてきました。レールについて、不気味な感情をいだきながらも。
しかしわたしはこの、目的地を話さぬ不思議な馬にまたがり続けているのがおそろしい。あるいは飽きてしまった。
(続く)
青鹿
ぽーん。
石を飛ばす、飛んでゆく、その軽やかな曲線を見つめながら、宮部はとなりを歩く伊木の横顔を盗み見た。いつだって彼らは連れ立って歩いていたので、わざわざ今、伊木の表情を確認する必要なんてない。たいしたイベントもない七月の終わり、夏休みモードに馴れ始めた倦怠をまとう身体をともなって、ふたりは歩いている。
「付いてこなくてもいいのに」
見つめられ続けながら、伊木はふたたび呟いた。用があるのだ、と宮部は淡白に返す。
用? 図書館に行くんだ。そんなのいつだっていいだろ、こんな朝早くじゃなくたって。友達と歩くのに理由がいるのか? そんな殊勝な性格してないくせに、よく言う。
じゃれた会話を切るように、伊木はため息をこぼした。
「なにか気になることがあるんだろ。言ってみろよ、今度はなんの霊が憑いてる?」
「べつに、たいしたことじゃないさ」
「お前の『たいしたことない』は、ぜんぜん、これっぽっちも信じられないんだよなあ」
言って、伊木は再び小石を蹴った。
重力に逆らって、たいした引力も斥力も磁力も電磁誘導も弱い力もないうちに、伊木はその小石を踊るように操っていた。まるで見えない透明な糸があるかのよう。いつだったか、宮部は伊木に尋ねたことがある。どうやって、石を動かすのか? 彼は答えた。
「どうやって腕を動かすのか、どうやって幽霊を見るのか、おまえ説明できるのか?」
問われて、宮部は完全に口をつぐんだ。たしかに、「できる」ことは「できる」から「できる」のだ。宮部が動物の霊を見ることが「できる」のと全く同じように。
理由なんてない。どうしてたった二本の足でもバランスを崩さずに歩けるのか、犬に聞かれても答えられない。どうして皮膚というやわらかい表層しか持たず、外殻を捨てているのに、毎月かすり傷をつくりながらも何とか生きていけるのか。どうして目が二つあって同じ方向を向いているのに混乱しないのか。あるいは爪も牙も保護色も足のはやさも持たない人間が、どうやってここまで繁栄を極めることができたのか――も。
「分からないことはどうしたって説明できない」
「ほんとうに大切なことは目に見えないのと同じように?」
「ファンタジーだな、伊木啓太。俺はゲーテの話をしたんだ」
伊木はもう一度顔をしかめ、そして唐突に笑った。彼はよく笑う少年だった。
「でも、俺にとって大切なことはたった一つだ。宮部、お前もきっと同意してくれると信じてる。ああウィルヘイム、この真実は決して変えられないということなんだ。俺は小石を意のままに動かせるし、君は動物の霊が見える」
「おおウェルテル。君は俺に手紙をあてて死ぬ男の役でもやるのか?」
伊木があまりに劇画的な物言いをするのに、宮部は半ば飽きかけていた。しかし彼の、括弧書きの台詞を唱えるような語り口には理由がある。単純に単調に、彼は演劇部の部員で、役者で、近々大舞台を控えているのだ。
手記と手鏡、それから
始まりは一通の手紙だった、と記憶している。
シェヘラザードは、冷岩によって作られた机の上で、ペンを躍らせていた。彼は武人だったが、書の読み書きが珍しくも出来た。一冊一冊を繰り返し発露させる彼の、白皙の感情。ただただ歌うように熱にうかされるように彼は文字を書き綴り、そして焼却していた。炎は彼にとって憧れの対象であり、酸素が失われるのを彼はこよなく愛していた。ふざけるまでもない、彼の愛情はあの炎の一点のきらめき、あるいは垂直の真昼、凍えるような暖炉のそばにあり、それ以外はすべて灰色の薄墨にぬりつぶされたつまらない戯曲の一節に落ちる。彼は言葉を欲していた。ただただ――そう、幸福になるためでも、財を得るためでもない。なにかしらの目的があるものでもなく、ただ、彼の手元のこの冷岩と同じく、そこにあるもの、ただ存在するものと一端として、その証左のためだけに、ペンが必要だったのだ。
彼にとって文字とは己の心のそのまま生き写しに他ならなかった。文章は生きている。文字を書くことは、魂を削り、紙面に命を吹き込むことであり、つまりは病をあえて発露させるような愚行でもあると、彼ははっきりと認識できていた。彼にとって文字とは、文学とは――――いや、もうやめよう。ただ彼の愚かさを少しでも希釈したく、わたしはこうして彼の異常なれまる執着について書いている。しかしこれは正しくない。本当に、真に彼に誠意を見せたいと願うなら、彼の愚かさは愚かさのまま、そのままに密封し決して酸素をいれず、ただ生ものとして取り扱うべきなのである。
そう、始まりは、一通の手紙だった。それ以外のなにも、彼の人生を壊す手がかりは存在し得なかった。文字に支配された彼の人生は、文字によって幕引きされる。そこまでをくるめて考えるのならば、彼が文字に魅了される性質を持って生まれてしまったその瞬間に、この数年にも及ぶ運命は決定されつくしていたといえなくもない。しかし、運命論は好きではない。すべてはあらかじめ定められていた――そうやって始まる物語ほど面白くないものもない。しかし、わたしが思うに、彼の運命はまさに決まっていたのだ。誰が毒牙にかかるのか。毒とはなにか。牙は何か――むろん、文字である。
物語を先に進める。シェヘラザードは気に入りの青インクをもう一度吸わせようと、ペンを取って壷の中へひたした。その落水の音が何よりも好きだった。シェヘラザードは愛情深い男だった。ペンが思うぶんだけインクを吸うのを、男にしては辛抱強く待った。その短い時刻のなか、彼は手持ち無沙汰の気を受けて、見慣れた机上をわざわざ見渡した。それが悲劇の始まりだった。彼は一通の手紙を見つけてしまったのである。
見覚えのない手紙だった。彼の身分に届けられるような手紙の場合、たいていは家紋入りの封筒が家名入りの封蝋で閉じられている。香がたち、それなりに威厳ある状態で存在しているのが常である。シェヘラザードにとって手紙はただの紙の束ではなく、ひとつひとつが契約を孕んだ宣誓書に値する。それゆえに、あまりに薄い封筒を彼は不審に思った。彼は手紙を取る。
(熱に浮かされながら 2017/11/08)
■
「魂」
「なに?」
ストアは持っていた本を持ち上げて、キスの顔を見る。機嫌がいいのか、今日は青いドーランが顔中にまぶされている。
「魂はどこへゆくと思う」
「僕は忙しいので、そこのクマに話しかけていただけますか?」
キスはクマを持ち上げて、同じ質問を繰り返した。あまりに哀れだったが、一度突き放した手前、ストアはなにも言わなかった。キスはやがて、杖でふわりと彼(クマ)を押し、空中に揺わせた。
「幽霊を君は信じるかね」
「信じません」
「魂の持ち回りは?」
「信じませんよ。魂からなにもかも」
*
「どうして突然姿を消したんです」
「勘違いかな。『どうして自分の前から勝手至極に消えうせたのか』と、君は僕をどうやら詰問したいようだ」
「質問に答えないのはあなたの悪い部分だとずっと思っていました」
「そうだな、悪かった。純然に悪かった。なぜ君の前から姿を消したのか、それはね、君に答えられるはずのないことを問い続ける自分の性分というものが嫌になったのさ」
「嫌に」
「そう。君がじゃない、君の前にいるときの僕のことを嫌いになったのだ。この違いは大変に大きく、そして君に最後に差し出せるヒントだ」
「あなたはときたま――いや、常に、僕に謎掛けをしている。いったいなにが楽しいんです。あなたはいったい僕に何を解いて欲しいんだ」
「問題すら明らかにならないのに、君はときに核心に至るようなことを言うね、ストア。だから好きだ。君のことは好きだ。ただ君の前でこうしてあいまいな態度を取るだけとって結局君になにももたらさない、そんな自分のほうこそ嫌いになったのだ。嫌気が差したんだよ、ストア」
*
「ねえ君、知っていたかね。魔術士というのは実は、作家なんだ」
「いえ、あなたは間違っている。魔術士は魔術士です」
「なんと面白みのない! 少しぐらい付き合ってくれないものかな」
「遊びたいならほかの人とにしてください」
*
「ねえ、まだ言わないの」
「なにをだ」
分かっているくせに、この人はどうしてこんなことを言うのだろう、と辟易する。
「師匠に言わないの」
「ストアに? 言わないさ! 何もね。何ひとつあの子は知らなくていいことだ」
師匠はどう見ても大人の男性なのに、彼をあの子なんて呼ぶ叔父のことが、僕はいっそ恐ろしかった。
*
「僕はあの人のことを心から信じてるよ」
僕も君にとってそういう人になれるよう努力するつもりだ、と言おうとしたがストアは、結局なにひとつ言えなかった。圧迫させてはならない。他人を威圧するために、僕は生きているんじゃない。そういうふうに思えることが僕の矜持だ。恵まれて生まれた僕の、最後の砦でこそある。
「僕はあの人のことを信じている……」
それはまるで自らを呪っているようなつぶやきでもあったが、それでかまわないとさえ思った。
呪われて構わない。
これは信仰のひとつだ。
三幕および四幕の断片より。
■
なめらかな曲線を描く書棚は、よくよく油のしみこんだ銘木イルゼナ材をまぶしい夕陽に光沢させていた。ところどころに掛けられている脚立は、細影をあしたか鶴のように伸ばしている。奥には巨大な窓でもあるのか、黄色の光が飛び込んでいた。ストアは目を細める。
黒の工房にも、大きな書庫があった。共用の本棚と個人の本棚が、区別されてはいたが同じ空間に並んでいて、ときにストアは知らない兄弟子の棚を覗いては、蔵書印を確認して拝借の交渉をした。ストアは貧しい農民の家に生まれた。村中の本をかき集めても、棚が作れるほどの冊数はなかった。ストアの常識では、本というのは湿気から守るために箱のなかに大事にしまっておくためのもので、決して背を曝して棚に並べるものではない。だから、抜き取るのが難しいほどぎゅうぎゅうに詰め込まれた棚を初めて見たとき、ストアは笑った。――まったく、世界が違うところに来てしまった。
キス・ディオールの書斎は、大きさでいえばそれほど巨大なものでもなかった。中央に円柱型の本棚が一つ、その周囲をやはり、本棚が取り囲んでいる。少々豪勢にすぎるバーバーチェアと、一点のシェーズロング・チェアソファだけが、わずかにこの部屋の主の存在を、真夜中に点った蝋燭のようにおぼろげに浮かび上がらせていた。これがなければ、国の指定遺産の部屋だと言われても信じられたかもしれない。椅子が貧相だというのではなくて――ただ、そう、個性的に過ぎた。書物に囲まれるなかにおいて唐突な存在であるところのバーバーチェアはもちろん、シェーズロングの大きさもなかなかのもので、ストアの体なら横になって休めそうなほどに長い。ふかふかで、家のベッドよりも寝心地はよさそうだ。家具の趣味はいいものの、やはり床面積は小さく、総じてささやかな部屋だと思う。ただ、わずかばかり上に長い。
見上げれば、とぐろを三回ほど巻いたような形をしている。上の上まで本は詰まっていた。最上の点、そこにだけ小さな天窓がしつらえてあり、編まれた紐が降りている。ストアは二階部分にあたる小フロアの棚に、懐かしい術本を見つけた。つい手に取りたくなって、どこから上がるのだろう、と不思議にあたりを見渡しても、どこにも梯子も転移石もない。
「やあ、気に入ってくれたかい」
あたたかな声が響いて、ストアは振り向かずにうなずく。
「はい、とっても――なんて素敵な書庫でしょう」
「と、言う割には何も手にとっていないじゃないか。上には小さいが書机もある。インクは好きかね? 僕は少々嗜んでいてね、ここからは見えないが、インク壷とペンとを、上の箱に展覧してある。よかったらご高覧あれ」
「――上に」
再びストアは、子供特有の細い首を伸ばして書棚を見上げた。ぷんと香る木材の香り、包み込まれるような古書の香り、それらに圧倒されながら、まだ見ぬ本はこんなにもたくさんあったかと、心動かされる想いだった。上に――。
「上に、行ってみたいのですが」
「行けばいい。誰も止めないさ」
「でも、どうやって?」
おやおや、と一段低い声でキスが歌うように言って、次いで指を鳴らす。それを合図に、ほんの一瞬だけ、床が足元から離れる――しかし浮遊感はない。重力も及ばないほんの一瞬だけ、床板がはずされて、またすぐについた、というような――不思議な感覚だった。
「君は『魔法』というものを知らないのかね?」
キスがそんなふうに笑って、よろめくストアの背を押した。深呼吸して、背後を振り返る。木製手すりが夕陽に黒光りしていた。バーバーチェアは眼下に転がっていた。ストアとキス・ディオールは、一瞬のうちにフロアを上がっていた。もちろん、魔法のちからで。
「転移石は使わないのですね」
「『転移』したのではない」
「では――移動?」
「その通り! とても早くね」
「飛んだのですね。軌道の計算がお早くて驚きました。二人いたのにぶつからずに――」
「いや、僕は計算がひどく苦手だ。そのせいでとんでもないことをやらかしたこともある。それに、もう一つ君は間違っているな――君が飛んだのではなく、この部屋が沈んだ。部屋のほうから来た癖に、どうしてぶつかる道理がある?」
「部屋が……? では、今、外の地面に、この書庫は沈んでいるとか……」
そうだとすると、気付かれないようにこれほど大きなものを一瞬で動かしてみせるなんて、あまりに巨大な力だ。ストアは身震いがしたが、キスはすぐに言葉を重ねる。
「いいや違う」
「違う、というのは……」
「動いたのは世界すべてだよ、ストア。しかしね、別にこれは今この一瞬だけの話ではなく、そもそもこの世界のすべての運動がそうなのだ。君や僕を中心に世界のほうが動いているのだ」
「そんなふうに思えということですか?」
「――また勘違いをしたね。違う、僕は真実を告げたのさ。思想の問題ではなく、真実の問題だ」
ストアは眉をひそめて少し考えたが、結局答えらしい答えを導き出すことは出来なかった。やがて所在無く漂わせた視線の先に、目当ての本を見つける。粉光をまぶしたように輝く、濃紺の上製本。
「青の本だ」
「えらいね。僕は君の年のころ、青も赤も終わらせていなかったし、なんならいまでも終わっているかどうか怪しい」
ストアは青の本を広げた。これほど美しい青本を見るのは久しぶりだった。青は基礎の本だから、たいていの術士はすぐに読み古して、硬く作られた上背も弱っていく。その分、傍らに置いて参考にするには便利だ。すぐに両手を広げてへたってしまう癖が、たいていの青本にはついている。
「僕はこの本の序文が好きなんです」
――呪文はいつも、自分だけを呪っているのだということを忘れるな。
魔術士の基本とされる一文。夢がないと非難する者もいるが、この一文はストアに大きな自信を授けた。魔術とは自分を呪うということ。自分をごまかすということ。公式はなく、ただ自分の心のありようと向き合うことだけを求められるもの。
「そうかい。僕は桃の本の序文が好きだ」
答えを意外に思って、ストアは首を傾けた。
序文を唱えようと開きかけた口を、キス・ディオールは制する。
「――ああ、いい。ありがとう優しい子よ。大丈夫、君がここで何を言っても言わなくとも、君の賢明さは十分僕の存ずるところさ。君がジョバンニなら、僕がカムパネルラだ」
何を言っているのか分からないままに、しかし制されたことで、ストアはキスに桃の本が好きな理由を聞けなかった。
(第二幕 二章 二節に続く)
■
啓太くんがサイコロをぐしゃりと掴んだ。
じゃらじゃらと手のひらの中でしばらく転がした後、いっせいに宙へ放り出す。
――賽は投げられた。
五つほどのサイコロが、好き好きに転がりながら、それぞれのタイミングでカタンと音を立てて停止する。面が揃ったとき、背中に悪寒が走った。
「これって、手品?」
「――ううん、俺が振るとこうなるんだ」
表を向いているのは、全て六の面だった。
啓太くんはこの奇跡をなんでもないことのように、手馴れた様子でサイコロを回収していく。
「っていうか、好きなように出来るよ。たとえば……栄子さん、誕生日十二月だったよね。何日だっけ?」
「十三日。金曜日だったらしいわ」
「六以下の数字だけだね。ちょうど良かった!」
四つだけサイコロを左手に握り、またじゃらりと投げる。
何の変哲もないはずの小さな立方体が、一、二、一、三……と止まった。
「凄い……これ、どうして」
「分かんない。五歳ぐらいの頃かな、やってみたら出来たんだ。あんまり大きすぎるものだと無理だから、商店街でやるような、大きなサイコロとかは駄目。あれがコントロール出来たら、一等の洗剤、毎回もらえるのになあ」
啓太くんはくしゃりと笑って、サイコロを再び回収していく。
「あの、浮かしたりはできないの? 例えば落ちているコインを触らずに持ち上げたりとか」
「ね。ほんとはそんなことがしたいんだけど、そういう力と、俺の力って種類が違うらしいんだ。同じ超能力――PKではあるんだけど、俺が出来るのはPK-MT。止まっているものを動かすには、PK-STって呼ばれる力が必要なんだって」
「PK……ああ、聞いたことあるかも。サイキックとか、ユンゲラーとか……」
「あはは、そうらしいね。俺はスプーンも曲げられないけど……それに、霊も見えないし」
「霊を視る力も、また別なの?」
「うん、あれは、超能力じゃなくて霊能力っていうくくりで、そもそも違うものなんじゃないか、って話が有力かな。たしかに理にはPKはないし、俺には霊能力がない。でも、両方出来る人たちもいるんだよね。あと、超能力者の子供は、小さいころ霊を視ることが多いらしいよ。だから、何かしらの相関は、あるんだと思う」
「でも……例えば両方持ってるって主張する人のことって、どの程度信じられるか分からないじゃない?」
「うん、そうだね。確かに超能力や霊能力って聞くと、ほんと胡散臭いしね」
啓太くんはサイコロをまたいじりだしながら笑う。
三つのサイコロを、すべて一、すべてニ、すべて三と、何度も揃えなおしていく。本当に奇跡だ。
「その……宮部くんと啓太くんのことは勿論信じてるんだけど」
「あ、別に気にしたりしないよ。まあ、普段はやっぱり、白い目で見られること多いし、あんまり言わないけどね」
「何か言われたことがあるの?」
「ううん、俺はあんまり。サイコロ揃えられるぐらいだし、周りにばれたところで、すげー! って言われて何度もやらされるぐらいで。でも、理は辛いこともあったんじゃないかなぁ。あいつは生きているものも死んでいるものも同じように見えるから、死生観、っていうのかな。そういうのも小さいころから考え出しててさ。そういう子供って、大人から見たらちょっと不気味に見えるんでしょ?」
確かに、そうかもしれない。理くんはそもそも頭がよさそうだし、きっと賢い子供だったんだろうな、と思った。その賢さが、両親や周囲の人々を不安にさせることだってあったろう。
まあ、栄子からすれば、今もまだ彼らは子供のようなものだが。
冷蛇第四話